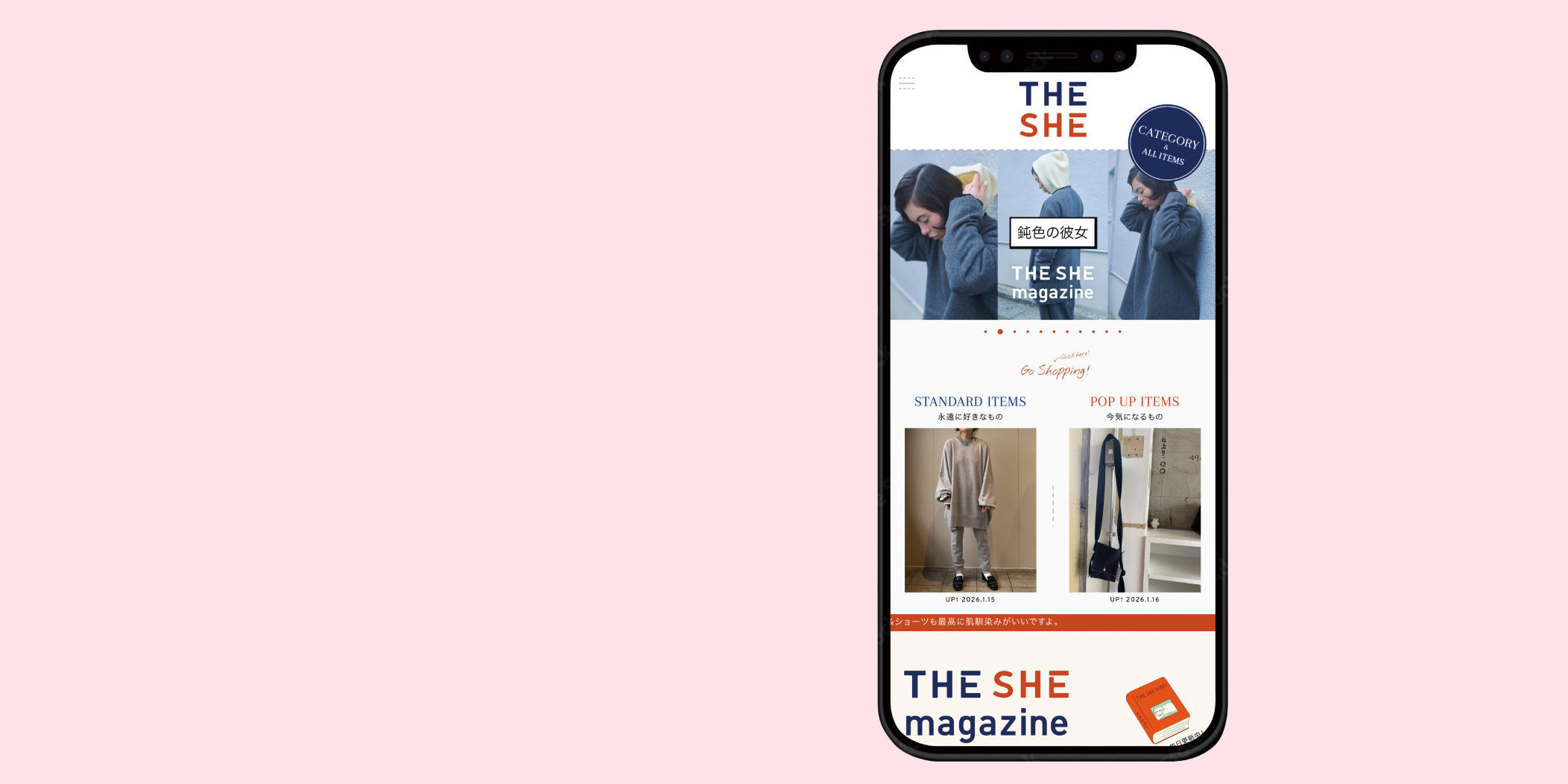+IPPO PROJECT
ファッションと福祉を楽しく繋ぐ
「プラス・一歩・プロジェクト」始動。

スタイリストの井伊百合子、フリーPRの枝比呂子とTHE SHEディレクターで編集者の渡部かおりが主催となり、+IPPO PROJECT(プラス・一歩・プロジェクト)をスタートする。これは、児童養護施設などを巣立った人たちのその後を支えるアフターケア相談所「ゆずりは」と手を繋ぎ、ファッションの持つポジティブな力をもとに、さまざまな形で社会問題につなげる活動だ。第一弾として、1月13日(水)にTHE SHEにてオンラインバザーを開催。様々な形でファッションに関わりのある人々に協力してもらい、愛用中の洋服や雑貨などを寄付してもらい、一部の必要経費を除くすべての売り上げ金を「ゆずりは」へ寄付するというもの。今回はバザーに先立ち、「ゆずりは」代表の高橋亜美さん、私たち3人の対談から、このプロジェクト始動の思いや背景、目標を紹介します。
(左から:渡部、「ゆずりは」代表高橋亜美さん、井伊、枝)

枝:昨今の子供にまつわる様々な悲しいニュースを耳にして、なにか私にも出来る事がないだろうかと思っていました。養護施設で育った子供たちの成人式で、着付けのお手伝いができたらと、着付けを習い始めたりもして。それで自立援助ホームにご連絡したら、コロナ禍中でそんな状況じゃないというお返事でした。年間で何度かやっていたバザーもできなくなって、来年の成人式の事は今考えられないし、どうなるかも分からないと。
井伊:そのタイミングで、自分たちが仕事にしているファッションを軸に、子供たちの未来へ繋がる何かをやるべきだよねという話になったんですよね。私も同じように子供を取り巻く環境とかどんどん格差が広がっていく社会に対して、どうしたらいいのかなという思いはずっとあった。それで、一緒に動いてくれそうだと思ったかおりさんに連絡をしたんだよね。
渡部:うん、二つ返事でOK、やろう! って言ったね。思うだけじゃなくて、すぐ行動に移そうって。THE SHEはそうやって誰かがなにかを始めるための場所になるというのも、一緒に運営しているプロデューサーのサチとの共通の目的でもあったからね。個人的にも、今、教育のボトムアップがなにより大切だと痛感していて、できることを探していたから。
枝:色々と調べていくうちに、様々な理由で養護施設で暮らしている子供たちは18歳で施設を出なくてはいけないという決まりがあることを知ったんです。
渡部:養護施設には寄付が集まっても、そこを巣立つ彼らへのケアは本当に手薄だった。
井伊:自分が18歳の時を思い出しても、まだまだ幼かった。両親に金銭的にも、精神的にもサポートしてもらうのが当たり前の環境だったことが、いかに恵まれていたかということを思い知らされました。それで、養護施設を出る子供たちへの支援を精力的に行っている団体をたくさん調べて連絡した中で、実際にお会いすることができてこの人と手を繋ぎたい! と思ったのが亜美さんでしたね。
高橋:本当に嬉しいです。ありがとうございます。
枝:寄付先は自分たちもそうだけれど、バザー参加にお声がけする中で、皆さんがすごく気にしている部分だった。直接、お返事をもらえてお会いして、たくさん思いを共有できたのが亜美さんでした。しかも亜美さんは井伊さんのことを以前から知っていたんですよね。
高橋:うん、そう! 連絡をもらって、わあ、スタイリストの井伊百合子さんだ!!って興奮しちゃった(笑)。
井伊:以前、<アルディーノアール>というブランドとのコラボレーションで、ブラックフォーマルを作ったことがあって、亜美さんが大切な仲間のお葬式にその洋服を選んで着て行ってくださっていたんです。
高橋:2年前かな、大森信也さんといって、『子どもの未来をあきらめない 施設で育った子どもの自立支援』という本を一緒に書き、養護施設を退所した子たちのサポートを本当に熱心に、身を削ってやってきた同世代の仲間だったんです。悲しい、辛いという思いもあったけれど、お疲れ様、これからの私を見ててね、という意味でも背筋をピンと伸ばして、さよならを言いに行けるセレモニードレスを探していて、これだ!と思って購入したのが、百合子さんの作ったものだった。
井伊:私はその本を読んでいたし、大森さんがお亡くなりになったことも当時のニュースで知って、すごく悲しくて。でも自分にはどうすることもできなくて、やりきれない思いでいたのですが、あの頃の行き場のなかった気持ちを亜美さんが着たドレスが一緒に連れて行ってくれていたのかもしれないと思ったら、胸がいっぱいになりました。スタイリストをやっていてよかったと心から思えたエピソードでした。
高橋:今回のご縁も大森さんが繋げてくれたのかもと思って、めちゃくちゃ嬉しかった。
枝:巡り合わせてもらってありがとうという感じですね。
渡部:うん、本当に。バザー開催の前に、今一度、亜美さんの「ゆずりは」の活動を、THE SHE magazineを読んでくださる人たちにお伝えしたいです。
高橋:はい。「ゆずりは」は児童養護施設や里親から巣立った人たちを対象にした相談事業をしています。児童養護施設などは原則18歳で退所をします。18歳、まだ未成年。高校に進学しなかったり、できなかった場合は15歳で退所を強いられることもある。長期的なケアが必要な子ほど早くに社会に出て自活するという矛盾がある上に、このアフターケア支援は、多くの施設で行き届いてないのが現状。家族の後ろ盾もない、虐待のトラウマも抱えている。そういう子供たちが自分の力だけで生きていくのは本当に難しいことで、借金を重ねてしまったり、女の子だと性産業に入ってしまったりしている。日本は、家庭という後ろ盾がないリスクが本当に大きいんです。
枝:亜美さんは、一緒に住む家を探したり、病院に付き添ったり、一緒に役所へ足を運んだり、本当に日々、相談者の方に寄り添って活動されていますね。あとは国分寺にアフターケア相談所のサロンも開かれていて、そこでは、様々な自立プログラム支援を行ってますよね。
井伊:私は、子供を虐待してしまう親の回復のための「MY TREEペアレンツ・プログラム」も実施していることにも感銘を受けました。親たちも実は傷を抱えていて、そのケアも重要ですよね。
渡部:まずばオンライバザーを実施することで、できるだけ多くのお金を寄付するという支援を選んだけれど、亜美さんに会って「私たちの考え、合ってますか?」って相談しましたね。
高橋:はい。やっぱりうちに相談に来る人たちは、基本的にみんな生活困窮の人たちばかり。お金は大丈夫ですという人は一人もいないくらい。家賃、生活費、食料支援、医療費、高卒認定試験。やっぱり、とにかくなにをするにしてもお金が必要というのが現状です。
渡部:今回はファッション関係者の人たちに声をかけて、洋服や雑貨を寄付していただきました。ファッションは、サスティナビリティという面でも真剣に向き合うべき状況だから、愛用していたアイテムをまた誰かに大切にしてもらえるという循環も、それか寄付になって社会に還元されるのも、理想的だと思ったんです。
枝:ただ自分だけに還元することじゃなくて、視野も人の思いもどんどん広がっていくというのが嬉しいよね。
渡部:うん。福祉とファッションはものすごく離れたところにあるイメージだからこそ、一緒に手を繋ぐことに意味があるとも思う。
高橋:仮にこれがバザーだとは知らなくても、記事を見たいから見る。かわいいから買う。その先で目的を知る。それくらいでもね、とっても嬉しい。
井伊:かわいいとか素敵とか、パッと目立つビジュアルとか。そういうエネルギーから社会問題に入っていくことはすごい大事ですよね。
枝:亜美さんの「ゆずりは」サロンで売ってるジャムもそう。別に背景を知らなくてもかわいいから買う、おいしいから買う。でも背景を知って余計に買いたくなる。そんな風でもいいと思う。
渡部:「かわいい」が誰かのきっかけ、気づきになれたなら、こんなに嬉しいことはないよね。ファッションに関わる私たちにとって、意味のあることだと思う。あと、亜美さんもおしゃれが好きでしょう! いつ会っても、自分らしい装いを楽しんでいるのが見て取れる。
井伊:この前も自分らしくいるために、自分の好きなものを楽しんで着ていると亜美さんが言っていて、それを聞けたことはとても嬉しかった。
高橋:福祉の世界って変にストイックというかね、身につけるもんなんて二の次だというムードが漂ってるんだけど、実際に「その服、かわいいね」なんてところから始まって、初めて会う女の子と深く話せることもあるんですよね。さっき、寄付してくださったアイテムの写真を見せてもらったけれど、私も欲しいものがいっぱいある(笑)。
井伊:参加していただいた皆さんがこのプロジェクトに快く賛同してくださって、集まったものばかりです。
枝:まずはオンラインバザー。3月にはポップアップイベントとして、実際に手にとっていただけるバザーも予定しています。他にも、ファッションのポジティブな力を使って、さまざまな活動に繋げていきたい。
渡部:とにかく楽しみながら、長く、長く続けていきましょう!

高橋亜美
たかはしあみ>>>アフターケア相談所「ゆずりは」代表。1973年岐阜県生まれ。日本社会事業大学卒業。自立援助ホームのスタッフを経て、2011年より「ゆずりは」所長に就任。著書に『はじめてはいたくつした』『嘘つき』『はじまりのことば』(すべて百年書房)、大森信也、早川悟司との共著『子どもの未来をあきらめない 施設で育った子どもの自立支援』(明石書店)などがある。
photo : Misa Sakuma text : Kaori Watanabe